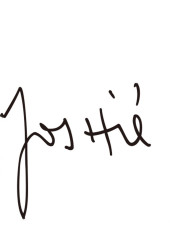ミニ大通の窓辺から
【2月の花コレクション】
2月の市場には、地中海沿岸原産の球根花や春の花木が並び、一足早く春が訪れます。店の景色も週替わりで変化し、一年の中で最も花の種類が豊富な季節。いうなれば、2月の花コレクションとでももうしましょうか。
まずは、2日のキャンドルマスに合わせた球根付のスノードロップ。そして、フリチラリアやヒアシンスを楽しめるのも、この時期ならではの特権です。続いて、14日のバレンタインに欠かせない、告白の象徴でもあるチューリップ。
また、希少なヘレボラス「フェチダス」を手にするため、コルシカ島風のレッスンを設けているのはいうまでもありません。さらに、春を感じるスノーボールやハゴロモジャスミンの鉢植えも店頭に並び始めます。(2026.2)
ミニ大通の窓辺から 2026
【ミモザをイタリアから】
花屋が「ミモザ」と呼んでいるのは、黄金色の小粒の花をつけたアカシアのことで、アカシアにはさまざまな種類があります。戦後、日本の花屋で多く扱われてきたのが銀葉アカシアです。札幌の百合が原公園の温室に大きな木があり、ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。
同じく札幌の滝野すずらん丘陵公園の「ぽかぽかテラス」にて新年から開花しているのはパールアカシアです。また、相思樹とも呼ばれる柳葉のアカシア・コンフューサは、台湾ではとても馴染み深い存在だといいます。
もっとも、ミモザとはオジギソウの学名ですが、南仏やイタリアで主流となっている房アカシアの羽状複葉の形がよく似ていることから、ミモザの名で呼ばれるようにありました。1月の下旬に、イタリアから届くこの房アカシアは、花が大きく、香りもひときわ豊かです。(2026.1)
ミニ大通の窓辺から 2025
【アボンヌモンについて】
アボンヌモンとは、フランス語でサブスクリプションというほどの意味で、店舗や事務所といった場所への花飾りの定期契約のことです。ご依頼を受ければ、まず下見をして、その空間でしか出来ない花飾りをご提案いたします。
たとえば、こちらのリストランテ/バーでは、その天井高を生かして、以前この欄でもご紹介したツェツェの「なまけものの花器」に花を飾ることを思いつきました。実際に食事をしながら閃いた花飾りのアイデアです。
過日、その考えを歌にしたので、ちょっと詠んでみましょうか。新年ですし。(2025.1)
肘掛け椅子(フォトゥイユ)に腰おろす仰ぎみれば緑を纏った「なまけもの」
【私の花器コレクション・13】
最近よく見かける「ディアボロ」という名の花器を知ったのは、今から25年ほど前のことで、四角い形のガラス器の中央に、大道芸が使う空中独楽のような窪みが花留めとなった花器です。奥行きもあって、花を投げ入れることも束を飾ることもできます。
デザインしたのはプロダクトデザイナーのマリアンヌ・ゲタンです。彼女は、当時パリにあった花屋「クリスチャン・トルチュ」のために、様々な花器を展開していますが、この「ディアボロ」は人気が高く、数年前に再販されて、現在でも手に入れることができます。
ちなみに、この写真左の透明な方は、スペインのメーカーから2010年頃に販売されたものですが、程なく販売中止になりました。その後、「ディアボロ」にはクリスチャン・トルチュのロゴが入ったのもこの一件があったからかもしれません。
(2025.2)
【近ごろのチューリップ】
春の花を代表するチューリップは花姿や色も豊富で、私たちの偏愛ぶりは17世紀から続いています。花屋において、最も品種が多く出回るのが3月です。彩度の低い品種が増えているのが近ごろの傾向でしょうか。
完全なるベージュ色のラ・ベルエポック、八重でフリンジ咲きのピンクマジック、紫と茶が混ざり合うウィンダム、その名の通り銅を連想させるコッパーイメージ、暗さの中に華やかさ漂うブラックヒーローという具合。
雪解けとともに、色とりどりのチューリップだけを束ねるレッスンを楽しんだり、アソートをご提案することにしたのも、近ごろのチューリップはこれまで以上に魅力的な品種が多いからです。手にすることで心が豊かになります。(2025.3)
【プライベートレッスンについて】
プライベートレッスンは今年から新しく加えたプログラムです。他のレッスンとの大きな違いは、その内容や受講する日時をあらかじめご相談して、ご希望に沿って行うことにあります。
たとえば、ブーケ・ド・マリエと呼ばれる、花嫁が持つブーケの作り方を学びたいとか、もっと基礎からスパイラルブーケに取り組みたいなど、より深く楽しむブーケ作りは個別対応ならではです。実例を見てみましょう。
こちらの方は、ブーケ・ド・マリエの年間プログラムをご希望されています。前回はチューリップを現代風に束ねていただきました。フランスの花様式に明るければ、この葉使いに、モニク・ゴーチェ先生を思い出すかもしれません。(2025.4)
【近ごろのカーネーション】
近ごろ、その印象が変わった花があります。カーネーションです。この写真のように、彩度の低い品種が増えていて、市場で見かけると思わず手に取ってしまいます。昨年からは、定期注文の花飾りにも使うようになりました。
また、この色目だとブーケにしても魅力的です。今月は初めてレッスンのプログラムにも加えてみました。茎が折れやすいので、束ねる場合は少し注意が必要ですが、ライラックや初夏の草花とは相性が良いかもしれません。
ちなみに、日本でカーネーションと呼ばれるようになったのは戦後のことで、それまではアンジャベルとかセキチクという名が一般的だったといいます。母の日にカーネションを贈るというアメリカ文化が伝わって、この呼び方が定着したのかもしれません。(2025.5)
【ドウダンツツジについて、その2】
今から2年前、この欄で「ドウダンツツジについて」と題していろいろと述べましたが、ひとつ大きな間違いがあることに昨年気がつきました。それは、花屋がドウダンツツジとして販売している多くは、その近縁種のアブラツツジだということです。
ドウダンツツジは花が咲くのと葉が芽吹くのはほぼ同時ですが、アブラツツジは葉が出てから花が咲きます。そして、この写真のように、そのベル状の白花はドウダンツツツジほど多くありません。枝ぶりも何やら涼しげです。
以前、お客様がこの枝を指して「家の庭にあるドウダンツツジと雰囲気が異なる」というご質問を受けることがありましたが、今後は迷わずお答えすることができそうです。(2025.6)
【ユリについて】
「カサブランカ」といえば、モロッコの都市を舞台にした映画を思い出す方が多いのかもしれませんが、花好きにとってはユリの品種として良く知られています。オリエンタル・リリーと呼ばれる白い大輪の品種です。
また「マルコポーロ」と聞けば、マリーアジュ・フレールの紅茶をまず思い浮かぶ方もいるでしょうが、花屋にとっては、「カサブランカ」とともに一時代を築いた、淡いピンクのユリの名として、懐かしさを誘う響きでもあります。どちらも今ではすっかり見かけることが少なくなりました。
代わって市場に並ぶのは、花粉の出ない八重咲きの品種「ハンバー」です。香りはなお強く、人によっては好みは分かれますが、凛とした姿には夏の魅力があります。ブーケにするなら、ヨウシュヤマゴボウとの組み合わせが一番です。(2025.7)
【アジサイを花留めに】
アジサイのブーケレッスンを一度でも受けたことがある方なら、このタイトルにピンとくるのではないでしょうか。房が集まってできているアジサイを使えば、ブーケは驚くほど簡単に仕上がります。
たとえば、この写真のように、細葉グミやローズゼラニウム、アメリカテマリシモツケをアジサイの房の間に挟み込んでつくる緑のブーケは、夏の余韻を感じさせる晩夏の定番です。ブーケづくりが初めての方でも、楽しく束ねることができるでしょう。
また、湾曲した茎を持つヨウシュヤマゴボウや、枝ぶりが複雑なブルーベリー、クレマチスのような蔓性植物も、アジサイと組み合わせることでうまくまとまります。暑い季節でも長く楽しめるアジサイは、ブーケづくりの頼もしい味方なのです。(2025.8)
【ダリア「カフェオレ」について】
最近出回るダリアの中でもひときわ目を引くのが「カフェオレ」です。淡いミルクブラウンからベージュへと移ろう花色は、光の加減でピンクを帯びたり、グレージュに沈んだりと、曖昧で複雑な表情を見せます。
写真の通り大輪で、束ねる際には少し工夫が必要ですが、秋の柔らかな光に映える姿は格別です。花弁を幾重にも重ねながら静かに揺れるさまは、まるで絵画の静物を思わせます。
もっとも、1968年にオランダで発表された品種ながら、市場で安定して出回るようになったのは近年のことです。そのため、確実に手に入れるには事前注文が欠かせません。今月のナイトレッスンやアソートで、その魅力を味わってみてください。(2025.9)
【受注販売から始まる、クリスマスリース】
札幌の冬は早く、10月になるとガーデナーは庭の手入れや翌春の準備に取り掛かりますが、花屋はクリスマスリースの受注販売を始め、クリスマスに向けた準備がスタートします。
受注販売とは、ご注文をいただいてから花材を仕入れ、新鮮な素材で制作する販売方式です。とりわけ、希少なコロラドモミを使うクリスマスリースは、今月中に市場へ発注する必要があります。
価格は7,700円。10月中旬から週間ほどで、お渡しは11月下旬、数量限定の販売です。写真は昨年のものですが、3種類の針葉樹とユーカリの蕾を使ったリースは、その冬の彩りが雪景色にも美しく調和します。(2025.10)
【ユーカリのリース2025】
オセアニアの異国情緒あふれる4種類のユーカリを使ったリースを作り始めたのは、2012年のことです。きっかけは、さまざまな品種のユーカリが入荷するようになったことでした。実のようにも見える個性的な蕾は、リースに驚きと華やかさを添えてくれます。
その後、SNSのInstagramを始めてみると、ユーカリだけのリースを作る花屋が世界中にたくさんいることを知りました。乾燥しやすいユーカリは、リースにすることでその特徴が存分に生かされます。花屋の発想は、万国共通なのだと感じたものです。
ポポラス、グロボラス、エキゾチカ、ロブスター。今回のリースで使用するユーカリの多くは輸入品のため、制作できる時期は限られますが、2025年は11月下旬のお渡しを目安に、11月1日より受注販売を承ります。おひとつ、¥7,700です。(2025.11)
【シースターについて】
オセアニアからの輸入花材として流通しているシースターファーンは、実は通称であり、正確な学名ははっきりしていません。ただその名の通り、ヒトデのような形をしたシダ植物です。
放射状に広がる葉は、乾燥しても美しく、年末のブーケやお正月のリース、そしてこのスワッグにも欠かせない存在となります。シースターがなければ、このお正月飾りは生まれなかったかもしれません。
さて、お陰様でミニ大通に根を付けて18年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
えっ、あれほど販売を拒んでいたミニブーケをChatGPTに促され、今月の催事に出品したところ完売したそうですねって?まあ、そんなことはいいっこなしよ。(2025.12)
ミニ大通の窓辺から 2024
【花のレッスン、色々】
花のレッスンには、技術を学びたい、資格やデュプロムを取得したいなど様々な目的がありますが、楽しみ続けることも大切です。ご要望にお応えするうちに色々増えましたので、少しまとめてみましょう。
まずは、レギュラーレッスン。事前に公開したプログラムに沿って、火木土に行います。スペシャリテはその豪華版です。
続いて、ショートレッスン。随時開催で、その時、店内にある花材で作ります。見本の製作はありません。
そして、市場レッスン。朝、市場で花を選び、店に戻ってブーケを作ります。市場見学付のレッスンです。花屋気分も味わえ、ちょっとした特別感があります。
最後は、ナイトレッスン。日中は時間が合わない方のために新設しました。平日19:00から行います。お仕事帰りの新たな楽しみです。(2024.1)
【フリチラリアについて】
舌を噛みそうな名前のフリチラリアは、ラテン語でサイコロを入れる箱というほどの意味で、碁盤の目模様の花弁からそう呼ばれています。西アジア原産で16世紀にヨーロッパへ伝わり、その後、オランダ花卉画の名脇役となりました。
その種類も豊富で、この写真のメレアグリスという品種が多く出回っています。花と葉のバランスが良く、単一で飾っても十分美しいのですが、この季節はヒヤシンスと合わせてみたいもの。オリエンタル風な仕上がりとなるでしょう。
ちなみに、開花時期も原産地も異なるバイモユリやクロユリもフリチラリアの仲間です。模様のある花弁や下向きに咲くベル状の地味な花姿、そして鱗茎を食用にすることなど、その特徴には類似点が多くあります。(2024.2)
【アソートについて】
先月から、ご自宅で花を楽しむ仕掛けとして、花材をあらかじめ組み合わせたり、取り揃えて販売するアソートを始めました。ブーケとの違いは、束ねていないことで、2種類のアソートをご用意しております。
ひとつは、「四月の花器、花材アソート」といって、ツェツェの四月の花器にそのまますぐに飾っていただけるものです。とはいえ、花材はバランスよく切り揃えてのお渡しですから、他の器でも楽しむことができます。
もうひとつは、レッスンの仕入れに合わせて手配するものです。たとえば、今月の「チューリップ、アソート」の場合、風変わりなものや希少性の高いものなど、様々な品種のチューリップに出会うことができます。アソートならではの楽しみ方です。(2024.3)
【スズランの器付ブーケ】
申すまでもなく、5月1日はスズランの日といって、この日にスズランを手にした人には幸運が訪れるという伝承があります。何でもフランスでは、誰でもスズランを売っても良い日だそうで、確かに、昔観た映画の中で、そんな場面があったかもしれません。
また、スズランにはもうひとつ特筆すべきことがあって、その釣鐘状の白い花数に決まりがなく、中でも、13個はより幸せだといいます。長年、この花を束ねる度に数えておりますが、確かに、100本のうち、2、3本見つかれば良い方でしょうか。
さて、今年のスズランのブーケは4月30日(火)と5月1日(水)、店頭に並びます。写真の器付は¥5,500、小さい束なら¥1,500です。今年も皆さんに幸運が訪れますように。(2024.4)
【グラミネについて】
グラミネとはフランス語で草というほどの意味で訳されますが、もっとわかりやすくいえば、イネ科植物の総称です。たとえば、花屋で売られているパニカム、ホルデューム、ワイルドオーツ、ススキなどはこれにあたります。
また最近では、この写真のように、名前がついていないグラミネも花市場で出回るようになりました。近年、シャンペトルと呼ばれる田園風のブーケが注目を浴びるようになり、多くの花屋がそういったブーケを作り始めたことが要因なのかもしれません。
この傾向、私にとっては嬉しいことで、これからの季節、ブーケ作りがより楽しくなるのいうまでもありません。早速、写真のグラミネは今月のレッスンで使ってみるつもりです。乞うご期待。(2024.5)
【夏至のブーケ】
聖ヨハネの誕生を祝う夏至祭にちなんで作る夏至のブーケは、夏至の頃に摘み取られた、太陽の光をたっぷり浴びた草花を用います。聖ヨハネの草とも呼ばれ、特別な自然の力が備わっていると信じられているからです。
その代表がセントジョーンズワートで、日本では西洋オトギリソウといいます。古代ギリシアから知られる憂鬱を解放してくれる薬草です。花屋で見かけるヒペリカムやビヨウヤナギは近縁種で、どちらも葉が異なりますが、花や実は似ています。
写真は、アネモネ・バージニアナ、カモミール、ノコギリソウなど、聖ヨハネの草による夏至のブーケです。その作り方は動画で公開しておりますが、今月は、夏至の日のナイトレッスンで、実演してお伝えいたします。(2024.6)
【ラベンダーのサシェ】
北海道中富良野町で収穫されたラベンダーの蕾を丁寧に摘み取って、手のひらほどの綿紗袋に、50gを詰め込んだのがラベンダーのサシェです。これは昨年から作り始めたもので、ラベンダーのタンバルの副産物でもあります。
サシェとはフランス語で匂い袋というほどの意味です。殺菌や虫除けとして実用性があるばかりか、クローゼットや引き出し、鞄の中に入れたり、洗い立てのタオルに挟んだりして、心を豊かにする知恵でもあることはいうまでもありません。
ラベンダーのサシェはおひとつ、1,100円。今月の下旬から店頭に並びます。ちなみに、ラベンダーの香りには安眠効果が期待できるそうです。昨年、寝苦しい真夏の夜に、このサシェを枕元に置いて何度助けられたことか。(2024.7)
【ブーケ・イスパハン】
2018年からレッスンのプログラムに登場したブーケ・イスパハンは、この写真のように、丸弁ロゼット咲きのバラ、ショコラ・ロマンティカを主役に、フランボワーズ、ブラックベリー、ミントを組み合わせた8月のブーケです。
イスパハンとは、世界遺産イマーム広場があるイラン中部の都市名で、古代ペルシアの時代からバラの街として知られています。19世紀にはロマン派の作曲家、ガブリエル・フォーレによって歌曲「イスパハンのバラ」が作られたほどです。
また、イスパハンという品種のオールドローズがあって、パティシエのピエール・エルメが、ローズシロップを使ったマカロンにイスパハンと名付けたのも、このオールドローズの品種名からだったと記憶しています。(2024.8)
【ナイトレッスンについて】
ご要望が多かった日没後の夜7時から行なっているナイトレッスンは、今年から加わったプログラムで、かれこれ半年が過ぎました。主に月に一度、金曜日に行なっていて、お仕事帰りのご参加が多い印象です。
この写真が示す通り、自然光が差す昼間のレッスンとは趣が変わり、照らし出された花や葉の輪郭が浮かび上がる店内は舞台装置の雰囲気を醸し出します。夜のミニ大通は静寂な森の佇まいとなりますから、よりブーケ作りに集中できるかもしれません。
ナイトレッスンはお一人様6,600円から。先月はヒマワリ、今月はダリア、来月はバラという具合に、特にテーマは設けず、月替わりで旬の花を束ねることにしております。(2024.9)
【近ごろのダリア】
ちょうど今から10年前のこの欄で、さまざまな品種のダリアが花屋に並ぶようになって驚いていることを述べました。その後はといえば、生産者も増えて多種多様なダリアが秋の市場を彩る状況で、名前を覚るのも大変です。
ただこれは、ブーケを作る上でとても良い傾向だとも思っています。冬のラナンキュラス、春のシャクヤク、夏のバラ、秋のダリアというように、その花の種類が増えるということは、季節の主役がはっきりするからです。また、束ねる楽しみも当然広がってきます。
たとえば、この写真のように、淡い色合い同士で組み合わせることも近ごろは簡単に出来るようになりました。この日は、ルル、シルキー、深山吹雪の3種類。とはいえ、ダリアを束ねる難しさは一向に変わりません。(2024.10)
【今年もマジックアマリリス】
今からちょうど2年前、お客様からのお問い合わせで初めて知ったのが、マジックアマリリスです。何でも特別に選別された球根で、室温が18度以上あれば水なしで成長して開花するといいます。オランダから届いたその球根は拳ほどの大きさがあるではありませんか。
錬金術師に騙された気分で、昨年一昨年と販売したところ、全てのお客様から何もせずに開花したという声をいただき一安心。その名の通り、魔術的に手をかざす程度で、入荷してから6週間ほど経つと咲いてくるというけです。
ひとつの球根から2本順に茎が出ますから、咲いてからも長く楽しめることでありましょう。今年も11月下旬頃から販売予定で、取り扱う花の色は白になります。場合によっては八重咲も入荷するかもしれません。(2024.11)
【稲穂飾り】
稲穂は、新年の始まりに家々を訪れる歳神様を迎える目印として飾られる縁起物です。豊穣や家の守護を祈る意味があり、場所を示す役割も果たします。
そこで、この秋に思いついたのがこの稲穂飾りです。既存の松飾りと同様に茎を藁で覆っています。紫稲も加えた2種類は、新たなお正月飾りといったところ。
おひとつ、800円。
さて、お陰様でミニ大通に根を付けて17年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
えっ、このコラムの冒頭のくだりは、AIによるものでしょうって?まあ、そんなことはいいっこなしよ。(2024.12)
ミニ大通の並木から 2023
【ラナンキュラスをコルシカ風に】
アプリコット色のラナンキュラスに、緑色のヘレボラス、それにオリーブの枝葉を加えれば、ラナンキュラスのコルシカ風の完成です。このブーケは花材が揃う期間が限られているため、2月のレッスンによく登場します。
コルシカ風とは緑色のヘレボラスとオリーブをブーケに加えた時の勝手な呼称です。どちらもコルシカ島に自生しているのでそう名付けました。もっとも、近年使っている品種のフェチダスは厳密にいえばコルシカ島原産でないというのはここだけの話。
ちなみに、このコルシカ風に限らず、19世紀風、田舎風、バロック風と、レッスンのタイトルは時に料理のメニューのような表記にしています。これは、ブーケ作りにはレシピがあって、料理に近いものと考えているからです。(2023.2)
【雪どけのリース】
笹葉のユーカリを土台に差し込み、オリーブとミモザを少し加えて、仕上げにハゴロモジャスミンとアイビーを絡めれば、雪どけのリースの完成です。春の日差しを浴びれば、複雑な緑の中に僅かな黄色が感じられます。
それは、雪どけの中から顔を出した草木が、意外にも色鮮やかだったり、福寿草の小さな黄色に気がつくあの嬉しい感覚です。もっとも、春のリースはなかなか閃かずにおりましたので、この新作に実は心が躍っております。
といいますのも、これはミモザが僅かしか入荷できなかった時、店内にあるもので偶然出来上がったリースだからです。 ChatGPTに「春のリースは?」と訊いたところで、こんな組み合わせはまだまだ教えてくれません。(2023.3)
【母の日に贈るブーケ】
今年の母の日は5月14日と、最も遅い日程で、ちょうど初夏の枝葉や草花が多く出回っている時期です。たとえば、この写真は昨年同日のブーケですが、ロゼット咲きのバラにリョウブとオルラヤ、スノーボールで仕上げています。
以前この欄で母の日に作るブーケについて「貰って嬉しくなるようなものに仕上げられるようになりました」と述べたように、この優しいロココ調な色合いは母の日に贈るブーケとしてぴったりでありましょう。
ちなみに、この組み合わせは作りやすさもあって、「ブーケ・マリアローザ」というタイトルで5月のレッスンでも行います。自分で作って手渡すことが出来るなら、これほど素晴らしい母の日に贈るブーケはありません。(2023.4)
【ヒメリョウブについて】
ヒメリョウブは別名がアメリカズイナというように、アメリカ原産の花木です。そのクリーム色を帯びた穂状花序は、ブーケのアクセントとなるばかりでなく、私たちに初夏の始まりを告げてくれます。
この写真のように、シャクヤクとの相性は抜群です。花の重さを、そのしなる枝がしっかりと支えてくれます。ブーケ作りは色合わせや季節感の他に作りやすさも重要ですから、この枝葉は5月の花屋に欠かせない存在でありましょう。
ちなみに、ヒメには小さいという意味があって、日本のリョウブより小さいのでそう呼ばれます。しかしながら、これらは全く別の植物であることを最近知りました。リンゴとヒメリンゴのような関係ではなかったわけです。(2023.5)
【ドウダンツツジについて】
これからの季節、ホテルなどの広い空間で見かけるドウダンツツジは、涼しげな新緑が私たちを爽やかな気分にさせてくれます。また、暑い場所でも花器の水が汚れにくく、長持ちすることもあって、ご自宅に飾る方も多いかもしれません。
しかしながら、購入する時期には注意が必要です。葉が柔らかい春先は萎れやすく、秋の美しい紅葉もすぐに枯れてしまいます。ぜひ、良質なものが出回る5月中旬から7月上旬にかけてお買い求めください。
それと、もう一つ気をつけたいことがあります。この枝を花束にはしないということです。切り分けて細かな葉をまとめてしまいますと、その魅力が台無しになってしまいます。潔くそのまま飾って楽しみたいものです。(2023.6)
【麦のタンバル】
フランスの花屋に古くから伝わる技法の一つであるタンバルは、円筒形の器に植物を覆って花器にする工夫です。ハランやマグノリアの葉で仕上げるのが定番ですが、時おり変化をつけて楽しむことがあります。
たとえば、今年初めて作ったのが麦のタンバルです。パン屋の周年祝いに合わせて3種類の麦でガラス器を包みました。これにブーケを飾りますと、麦の素朴な美しさが、白いバラをより華やかに引き立たせてくれるのはいうまでもありません。
写真左、ブーケとのセットは7,700円から。写真右、麦のタンバルはおひとつ、3,300円。今月はエピ・ド・ブレといった麦にまつわる行事もありますから、パン屋に限らず夏の贈り物としてもぴったりでありましょう。(2023.7)
【市場レッスン】
「仕入れ」「水揚げ」「ブーケ作り」といった3つの内容から成り立つ市場レッスンはこの夏から加わったプログラムです。「仕入れ」は市場に行って、作るブーケの花材を、その秘訣を聞きながらご自身で選んでいただきます。考えるレッスンとも呼べましょう。
続いて、店に戻って「水揚げ」を、その仕方を教わりながら行います。これは知るレッスンという位置づけです。そして、花材を最初からご自身で準備した「ブーケ作り」は、これまでのレッスン以上に、学ぶレッスンとなるかもしれません。
市場レッスンはお一人様、60,500円。毎週金曜日の朝6時から始まる、ブーケ作りにおいて最も大切な、束ねない時間からの330分。きっと花屋の気分が味わえます。(2023.8)
【ザクロのリース】
華道などの需要もあって、この時期に市場で時々見かけるのが果実のついたザクロです。枝ぶりにもよりますが、ずっしりと重たい果実は、ブーケにするには少し難しいので、数年前からはこのようにリースにして楽しむことにしています。
作り方は他のリースと同様で、環状にしたサンキライの枝に、小分けしたザクロの枝を絡めていけば完成です。この写真は出来立てですが、乾燥しても葉色が少しくすむ程度で、その雰囲気は何ら変わりません。
ちなみに、ザクロは北海道では育たないので、私にとってこの果実はどこか異国情緒を感じます。なにしろ、花屋になるまで、セルゲイ・パラージャノフの映画の中でしかザクロを知らなかったわけですから。(2023.9)
【スレッズとレッスン日誌】
新しいSNS、スレッズで時おり投稿しているのがレッスン日誌です。その名の通り、レッスンで使った花材と出来上がりの写真を添付して、その意図や作り方についてこのコラムほどの長さで述べています。
なぜスレッズなのかといえば、このSNSにはミニブログの要素があって、文書と写真が見やすいプラットフォームとなっているからです。スマートフォンからも読みやすく即時性もありますから、花屋にとって、これはとても適している気がしました。
もっとも、インスタグラムもレッスンの内容をお知らせする目的で8年前に始めたわけですが、写真共有アプリゆえ文章との親和性が高くはありません。スレッズの登場で、お伝えしたいことがより充実したわけです。(2023.10)
【スキミアについて】
日本原産のスキミアはヨーロッパで品種改良された園芸品種です。晩秋から冬に咲き、この写真のように蕾が緑色の他に赤色があります。欧米ではクリスマスの花としても親しまれていて、花屋に並ぶものの多くはオランダ産です。
何でも、ロンドンの花屋に勤めていたお客様の話によれば、イギリスのクリスマスはポインセチアではなくこのスキミアを飾るのが一般的だそうで、この時期の花屋はスキミアの鉢植えだらけになるというではありませんか。
そういえば、ミニ大通に面したマンションの花壇には立派なスキミアが植えられていて、雪の中でも堂々と咲いていますし、店から車で1時間ほどの野幌森林公園には野生のものが見つかります。スキミアは冬の身近な花なのです。(2023.11)
12月【ガレット・デ・ロワと3つのブーケ】
エピファニーにちなんだこのレッスンは、小さな3つのブーケを作って卓上に並べて飾り、ガレット・デ・ロワを楽しむというものです。目覚めを意味するアーモンド菓子を味わいながら、3人の王様にちなんだ植物とともに、1年の幸運を占います。
もっとも、切り分けたフェーブが当たらなかったとしても、私自身はこうやって、レッスンを続けられることが既に幸運であることはいうまでもありません。
さて、お陰様でミニ大通に根を付けて16年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
えっ、今頃は韓国にいるはずなのに、何故か日本で呑気にコラムを書いているって?まあ、そんなことはいいっこなしよ。(2023.12)