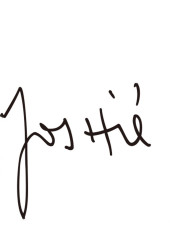ミニ大通の並木から 2012
【ラッパスイセンのブーケ】
ホメロスの詩にもあるように、スイセンの花は春の蘇り、すなわち復活の象徴です。そういったこともあって、新年に作るブーケには時おりスイセンを用います。ただ、新年を迎えるスイセンが凛とした白い房咲きを使うのに対し、年が明けた頃からは春の暖かさが感じられるラッパスイセンの登場です。
写真はちょうど今から1年前に束ねたもので、ネコヤナギ、ビバーナム、キヅタ、ミルトといった旬の枝葉がこの早春の花を引きたてます。もっとも、黄色い花はふだんあまり扱うこがありませんが、ミモザやヤドリギの果実がそうであるように、雪の中に見る明るい黄色は美しいものでありましょう。
ブーケはおひとつ、¥4,200から。そういえば、ラッパスイセンはウエールズの国花で、テレビのラグビー中継を観ていると、この時期に限っては、この花を胸元に飾って応援する女性達の姿があります。素敵な習慣です。(2012.1)
【ガラスの鉢植え】
花市場に並ぶプラスチックに入った小さな鉢植え。これを仕入れて、そのまま売るのではなく、ちょっと洒落た感じに仕上げるためには二つの方法があります。ひとつは素焼きの鉢に植え替えて、マグノリアの葉などで包むやり方。もうひとつがこのガラス器に移して土や根を見せて楽しむというものです。
たとえば、写真のガラスの鉢植えは、左からスノードロッ(¥1,050)、ベビーティアーズ(¥750)、クローバー(¥950)になります。きっと私のように、雪の中で暮らす人にとって、この時期に見る土は近づく春を連想するのではないでしょうか。
もっとも、穴の空いていない器で鉢を育てるのは難しい、と思われるかも知れませんが、小さい鉢植えだからこそ、週に1度の間隔で土を湿らすだけで上手くできます。斯くて、ベビーティーアーズをいつも枯らしていた私がこのやり方で失敗しなくなったのですから。(2012.2)
【イチゴのブーケ】
イチゴのブーケを作ることができるのは3月から4月。なぜかといえば、この時期に出回る鉢植えを切って束ねるからで、それも果実がまだ熟さないような青い状態であることが重要。食べて美味しいものを、そこまでしてわざわざ仕上げるのは、バロック時代に生まれたこの果実の小さな花束がそれだけ魅力があるからです。
もっとも、イチゴはバラ科の多年草で、本来、スズランが咲く頃の果実でありますが、陽気が暖かくなるにつれてイチゴを目にしますとやはり春の訪れを感じることでありましょう。イチゴのブーケはおひとつ、¥2,100。この春も少しだけ登場します。
ちなみに、イチゴは野イチゴやラズベリーなどを元にオランダで生まれ、江戸時代にオランダイチゴとして日本に伝わった比較的新しい果実で、当初は食用ではなく観賞して楽しむ植物であったことはあまり知られておりません。(2012.3)
【花の仕入れ】
花の仕入れは朝5時30分、いや最近は6時過ぎに札幌市内から約10km東にある花市場へ週に何度か足を運びます。とりわけ、切り花のセリが行われる月・水・金は欠かしません。私のような小さな花屋は、料理人が食材を選ぶような感じで仲卸業者を回ります。
出来上がるブーケを想像して、自分の目と経験から確かなものだけを選びますが、ミルトやマグノリアなど市場になかなか入荷しない花材は注文して手に入れています。もっとも、近頃は冬にバラやシャクヤク、春にダリアやアジサイ、夏にクリスマスローズが出回り、花屋は誘惑されることもしばしば。
でも、季節に正直な枝葉から選べば、変な間違いは起きないというもの。あとはイチゴのように、その季節、店内にあって楽しいかどうか、これが重要。たとえば、4月30日ならスズランを仕入れ、明日の幸せを準備するわけです。
(2012.4)
【レッスンのプログラム】
お気付きの方もいらっしゃるかもしれませんが、レッスンのプログラムは、その時期に店の主役となる花に基づいて組まれております。そこで、この5月に並ぶ店の花について、プログラムを例に、ちょっとご紹介してみましょう。
ます1週目はスズランの幸せ。小さなブーケが幸せを運ぶ1週間です。続いて2週目はバラを母の日に。優しい雰囲気のものや香りの良い品種が揃います。3週目はそろそろシャクヤクを。そして、4週目には値ごろになったシャクヤクをたっぷりと、といった具合です。
ちなみに、昨年の11月からテーマを週替わりにしてレッスンの種類を増やしました。理由は簡単で、プログラムを考えるのが私の密かな楽しみだからです。写真は、4月の後半に旬を迎えるスイートピーとアジアンタムで、最近のレッスンから。(2012.5)
【野原の季節】
初夏の花屋は野原の季節。デルフィニウム、スカビオサ、カンパニュラ、クレマチス、オルラヤなどの草花が店に溢れます。作るブーケも、他の季節とは異なって、シャンペトと呼ばれる、田園から摘んだような雰囲気です。
たとえば、写真のブーケは劇場の入口にと依頼されたもので、私にしては珍しく青い花を中心に束ねています。1メートルほどの大きさです。まさに野原といった感じで、出来上がったブーケを店の前、すなわち、ミニ大通りに置いてみますと、まあ、ぴったりなこと!
もっとも、ミニ大通りは今がとりわけ美しい季節です。新緑の輝きやが目を喜ばせ、鳥の鳴き声や、葉音が耳を楽しませます。そんな自然のBGMが流れる環境の中で、オリーブやアジアイの鉢植えを店先に並べ、手の中で野原を作るのが6月の私。(2012.6)
【花のコロネ】
市場でアンスリウム・クラリネビウムの葉を見つけたら、花のコロネを作ってみたくなります。このコロネとはフランス語で円錐形というほどの意味で、たとえば、ハムのコロネといえば、サラダをハムで巻いたものですし、チョココロネという円錐形のパンは皆さんも良く御存じでありましょう。
もっとも、花のコロネは、今から17年ほど前にフランスで刊行された子供向けの花の絵本にその作り方が載っております。ここでは緑色のアンスリウムの葉で花を巻いておりましたが、写真のように、私のコロネは、同じアンスリウムの葉でも縞の入った品種です。
ベルベットを思わせる手触りのこの葉は、たとえば、白いラシラスの花を包みますと、涼しげな雰囲気となります。まあ、ちょっと風変わりな夏の小さな贈り物というわけです。花のコロネはおひとつ、¥1,260。さて、明日はこの葉が見つかるかなあ。(2012.7)
【「山採り」の山ブドウ】
写真にあるように、山ブドウ、すなわち野生のブドウが入荷するのは札幌の短い夏が終わろうとしている8月の半ば頃です。この枝物は栽培されているわけではなく、ヤドリギなんかと同様に「山採り」と呼ばれる業者がこ
の季節、文字通り山から採ってきます。
この「山採り」。花屋にとってはとても貴重な存在で、ブーケや花飾り、そして店の雰囲気は、彼らのおかげで季節感と自然さを得ることができます。なんでも、フランスには、フォイヤジストと呼ばれる葉物や枝物を提供する業者があるそうで、「山採り」はまさに日本のフォイヤジストでありましょう。
ちなみに、今年はそんな「山採り」による山ブドウで直径約30センチのリースを作ることにしました。名付けてバッカスのリースで、おひとつ、¥3,150。壁に掛けて飾るのも良し、頭にのせてワインを楽しむのも可笑し。まあその出来栄えは今月下旬の店頭にて。(2012.8)
【ブーケを飾るガラス器】
以前、「こういったスパイラルブーケを飾るのに適当な器はどこで売っていますか?」といったご質問をよく受けました。探してもなかなか見つからないという話なので、私も探してみたところ、口が細かったり、高さがあったり、模様があったり、円柱でなかったり、高価だったりと、たしかにありません。
そこで、ちょうど1年前にやっと見つけたのが、写真のガラス器です。直径9センチ、高さ20センチは、レッスンで作るブーケはもちろんのこと、たいがいのブーケを飾るのにはぴったりで重宝します。ブーケを飾るガラス器は、おひとつ、¥1,050。手ごろな価格も大切でした。
もっとも、こういった器が必要だというのも、近頃は、自宅にブーケを、それもスパイラルブーケを飾る人が増えてきたということでありましょう。花の組み合わせや、花器とのバランスを考えて活けるのとは違って、ブーケにはポンと飾るだけで部屋の雰囲気が変わる手軽さがありますものね。(2012.9)
【枝葉のブーケ】
申すまでもなく、この店で束ねられるブーケの約8割は白と緑の色合いですが、次に多いのは、緑だけの組み合わせです。枝葉のブーケといった方が良いかもしれません。写真のように、ドングリとユーカリをたっぷり束ねることもあれば、イネ科の植物をちょっとアクセントに加えることもあります。
また、テマリシモツケのような銅葉色などもこのブーケにおいては大切な要素で、緑の濃淡だけで束ねる場合とは違った趣になるというもの。いずれにせよ、少し控えめながら、自然が溢れるように作るのが枝葉のブーケの特徴です。
もっとも、花らしい花をあえて用いませんから、このブーケ、派手さからは遠ざかります。でも、枝葉というのは季節に正直ですし、長く楽しめるものです。ちなみに、美しい枝葉は花の少なくなる秋から冬に充実しますから、枝葉のブーケは今が旬なのであります。(2012.10)
【私のリース作り】
何だか、雑貨や工作のように思えて、リースぎらいで通っていた私が、どういう風のふきまわしか、このところ、気軽にリースを作るようになりました。一昨年のクリスマスのリースに始まり、今年に入ってからは、月桂樹、ミモザ、時計草、山葡萄、豆柿でも作り、自分でも「ほぉ」と驚いてしまいます。
柳などを環状にした土台に、鳥が巣を作るように、枝葉を絡めて仕上げる私のリース作り。むろん、針金や接着剤などは使いません。そのため、ブーケのごとく立体的に仕上がります。作家の荒俣宏さんは、現代の花束は古代ローマのリースが起源と指摘していましたが、なるほど、リースもブーケの一種なわけです。
この冬は、モミやネズの枝葉などでクリスマスのリース、さまざまなユーカリによるリース、松やナンキンハゼの白い実を使ったお正月のリースを作ります。また、リースを主役にした舞台飾りを行うなど、私のリース作りは、どうやら、しばらく続きそう。(2012.11)
【お正月のリース】
数年前から、年末に実付きのオリーブが出回るようになり、この冬初めて作ってみたのがお正月のリースです。環状にした小豆柳を土台に、譲り葉、シースター、オリーブ、南京櫨を、鳥の巣のごとく立体的に絡めます。そして、大王松の葉を、現代風フランス料理の一皿を思い出して盛り付ければ完成です。
伝統的な縁起植物と、その植生から導き出した松とオリーブの組み合わせは、仄かにお正月や地中海の初日の出が感じられます。南京櫨の白い実も愛らしくて、これなら、七草粥を食べた後でも、しばらく飾って楽しめそう。おひとつ、¥3,800(直径約28センチ)。
さて、ミニ大通りに根を付けて5年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞ宜しくお願い致します。
えっ、先日このリース作りのレッスンで、見本製作を失敗したって?そんな事はいいっこなしよ。(2012.12)
ミニ大通の並木から 2011
【ヤドリギ】
私の冬の楽しみの一つはヤドリギ探しです。歩きながら、あるいは車を運転しながら落葉樹を見上げてはこの寄生植物を探します。見つけた時は、名高いフランス文学者のごとく「あ、ギーだよ。」とフランス語で叫ぶか、万葉の歌人のごとく「ほよ」と古名をいいながら、その姿や実の色を観察します。
そんなこともあって、先日依頼された「森の分室」と称した花飾りでは迷うことなくヤドリギを飾りました。古代ケルト人のドルイドやアイヌの人々が崇めてきた縁起の良いこの植物によって、神々しい冬の森の空間に仕上がったというわけです。
ちなみに、店の近くにヤドリギは近代美術館敷地内の樹木にありますが、残念ながらミニ通りの樹木にはありません。でもミニ大通りの花屋にはございます。ただしこちらのヤドリギは高価なこともあって仕入れるといつも店内に宿ったままなんだなあ。(2011.1)
【ミモザを窓辺に飾って】
ミモザは、パリのスーパーでおじさんが黒いラッピングをして売っている印象が強いし、他の花材との組み合わせが不向きなこともあって、以前はあまり扱わない花でした。ところがこの時期、ウインドーにミモザを飾ってみますと、雪の積もったミニ大通りに黄色い小粒が輝いて、これがすこぶるよろしい。
春の訪れといいますか、少し大袈裟にいえば、店内に南仏コート・ダジュールの暖かさが運ばれてきた、という感じになります。もっとも、福寿草がそうであるように、雪の中で見る黄色は、北国に住む私たちの気分を良くしてくれる情景でもありましょう。
そういえば、1968年のグルノーブル冬季五輪の記録映画『白い恋人たち』で、ミモザだけを束ねた表彰式のブーケを観ることができます。旬の花だといえばそれまでですが、あの色が銀世界に映えることを、フランスの花屋もきっと知っていたにちがいありません。(2011.2)
【白い花あそび】
「うちの店でレッスンをしていただけませんか?器やアンティークのものに、ちょっとした花あしらいを提案してほしいんです。」
「なるほど、それは面白そうですね。春は始まりの季節ですし、やってみましょう。」
「良かった、宜しくお願いします。」
「それで、レッスンが11時開始でしたら、その後は2Fのカフェでランチですか?」
「はい、タルティーヌをご用意しようかと。」
「タルティーヌ!良いですね。少し温めた1センチ厚のカンパーニュに、菜の花のソースを塗って、サン・ジャックやディル、ピンクペッパーをのせたりしてね。」
とまあこんな具合で、ランチ付きの出張レッスン「白い花あそび」が始まります。(2011.3)
【春のミニ大通】
たしか、バルザックかミシェル・ブラスのどちらかが著書で「自然はたゆまなく繰り返す」といっていたように、もうすぐミニ大通りにも春がやって来ます。4月の始めまであった雪がなくなり、いつの間にか木々の芽吹いた緑が目立ち始め、5月の連休には桜やレンギョウに彩られるというわけです。
もっとも、ミニ大通に桜は西11丁目から西16丁目まで植えられていて、どういうわけか、店のある西17丁目には樫やクルミ、姫リンゴといった果樹しかありません。まあ、私がいる場所ですから、樹々に咲く花も白や緑ということなのでありましょう。
では、ミニ大通の花屋はどうかといえば、春が訪れますと初夏の花が旬になります。冬に春の花があるように、花屋は一足先の季節を提供するものだからです。写真のように、4月の中旬から母の日の頃のブーケでは、薔薇、ウツギ、ソケイが主役です。むろん、5月1日はスズランが今年も主役ですけどね。(2011.4)
【ムング豆のボール】
ポリスチレンにムング豆を張り付けて作るこのオブジェは、今から15年ほど前にフランスで出版された子供向けの花の絵本でも紹介されていたことがありますから、ご存じの方もいるかもしれません。
その作り方は単純で、まず直径10センチほどの球体を両面テープで覆い、次に皿に盛ったムング豆の上で転がしながらある程度まで豆を球体に張り付けます。そして、隙間をひとつひとつ埋めていき、仕上げにエスプレッソ粉ほどに砕いた木屑をまぶして豆の隙間が目立たなくなったら完成です。
少し手間はかかりますが、パズルが出来上がったような爽快感が味わえるのがこのオブジェ作りの楽しいところ。ムング豆のボールはおひとつ、¥1,890。こういったオブジェは花や緑を引き立たせる役割がありますから、フランスでは子供向けの本にだって登場するのでありましょう。(2011.5)
【夏至祭のリース】
クリスマスが太陽を励ます冬至の行事であるならば、夏至祭はその対極にあって、強まる太陽に感謝する日であることはいうまでもありません。すなわち、どちらも生命の祝祭であるわけですが、それなら、夏至の日にもリースがあって良いのではないか、ということで出来上がったのがこの夏至祭のリースです。
プリニウスの時代からある花装飾のごとく、リースは環状に束ねたアイビーに木棒を付けたのが特徴で、夏至祭の時に広場に立つマイバウムを模しています。壁や扉に掛けるのではなく、花瓶や鉢植えにさして空間を飾れば、部屋の中で夏至祭の気分となりましょう。
夏至祭のリースは、おひとつ、¥1,260。リースの直径は約18センチですが、棒の長さは90センチと、ちょっと持ち運びにくいのはご愛嬌。ちなみに、ガラスチューブで保水しておりますから、夏至の前夜に摘んだ聖ジョンの草をここに飾っても素敵です。(2011.6)
【オリーブの鉢植え】
部屋の中に置く緑の鉢植えを選ぶ時、大切なのはその環境に適したものを選ぶことです。たとえば、私が住む北海道の室内の場合、夏は湿度が低く、冬は暖かく乾燥しています。いわゆる、高温多湿な亜熱帯地域が原産の観葉植物なんぞは、案外育てるのに手間が必要かもしれません。
そこで、オリーブの鉢植えの登場です。皆さんも良くご存じのように、平和の象徴であるオリーブは地中海性気候の植物で、1年中暖かさと乾燥を好みます。すなわち、北海道の室内環境と似たところがあって、これが育てやすいというわけです。
オリーブの鉢植えはおひとつ、¥5,250。忘れない程度の水やりで管理できます。クネゴの復活を信じてツール・ド・フランス観戦で家を空けるという方も嬉しいかぎり。もっとも、私は今年もテレビで観戦。(2011.7)
【トルミネアの鉢植え】
たとえば、ミシェル・ブラスのミルクジャムが冷蔵庫に入っていれば、いつものパンがより美味しくなるように、このトルミネアの鉢植えがあれば、家の中で花をちょっと飾る際、葉を鉢から摘んであしらうだけで、その花飾りは美しく洒落た感じに仕上がります。
まあ、その昔はクリスチャン・トルチュがスイートピーの小さなブーケを作る時に、最近ではカトリーヌ・ミュレーがテレビのフラワーレッスンで用いていたように、トルミネアは、夏の光を思わせるその明るいマーブル模様の葉で私たちの気分を良くしてくれる、というわけです。
トルミネアの鉢植えはおひとつ、¥1,260。花飾りやブーケ作りにおいて、常備しておくと便利な魔法の葉っぱです。ちなみに、庭に植える場合、この植物は北米西海岸の森林の下草だといいますから、湿り気のある日陰が適しています。(2011.8)
【ダリアのブーケ】
たしかに、切り花にしたダリアは長く楽しめるわけではありません。けれども、季節の花を楽しんだり、贈ることを考えるならば、ダリアはやはり魅力的です。とりわけ、秋に向けてさまざまな実が目立ち始めるこの時期は、その華やかさが一層増してきます。
たとえば、小さなナスやリンゴ、野バラ、山ゴボウ、シンフォリカルポス、ホオズキなどと束ねたダリアのブーケは、いかにも秋の田舎の風景といったところ。もっとも、花嫁向けであれば、写真のように白いポンポン咲きに、ドングリなんかでまとめるとちょっと素敵でありましょう。
そう、ダリアといえば、エミール・クストリッツァの映画『黒猫・白猫』を思い出す人も多いかもしれません。ラマの音楽にのせて、秋の陽光に輝くダリア畑。私はブーケを束ねる時、その花が咲いている情景を頭の中に描きますが、ダリアに関してはいつもこの場面。
写真は今から10年ほど前に作ったダリアのブライダルブーケです。白いポンポン咲きのダリア、アイビー、ドングリの組み合わせは、今見直してみても新鮮な気分。もっとも、最近では黒い“黒蝶”など、ダリアも束ねたい品種がずいぶん増えました。(2011.9)
【出産祝いのブーケ】
出産は新しい命の始まりでもありますから、そのお祝いのブーケではラナンキュラスやシクラメン、スイートピーなど春の花を加えて作るのが基本です。でも、だからといって、季節感がなくなってもいけませんので、夏から秋の頃にはバラで、それも大輪は避けて、蕾や小さなものを使うようにしています。
また、ブーケの色合いについては、私に依頼すると、とかく白と緑になりがちですが、大切なのはフレッシュであること。そして愛情や優しさが感じられる印象に仕上げることでありましょう。出産祝いのブーケはおひとつ、¥5,250から。
写真は秋に作ったもので、小さなバラに姫リンゴを加えて、器は藁で巻いています。申すまでもなく、お祝いのブーケは、そのまま飾ることができるように器を付けた方が贈られた相手には喜ばれるもの。とりわけ、出産祝いにはこの手法がぴったりです。(2011.10)
【モスのボール】
球体のオブジェについては、以前に、マグノリアの葉やムング豆を素材にしたものをご紹介しましたが、そもそも、こういった飾り物として最初に作ったのがこのモスのボールです。モスとはいわゆる苔のことで、これもポリスチレンを土台にして仕上げます。
使っている苔は自然乾燥させた、トルコ産で板状のシートモスと、オランダ産で塊状のプールモスと呼ばれているものです。とりわけ、凹凸感を持つプールモスのボールなんぞは、「法然院を思い出すわ」と京都の美しい苔を知る方なら心が動くにちがいありません。
モスのボールはおひとつ、シートモス製だと直径25センチ(大)が¥5,250、直径15センチ(小)が¥3,150。プールモスだと直径20センチが¥7,350。
ちなみに、生命を象徴する苔もクリスマスに飾る緑のひとつです。(2011.11)
【新年の松飾り】
松の枝を藁で包み、アクセントに南京黄櫨の白い実を飾れば新年の松飾りの完成です。写真のように、壁に掛けるのも良いものですが、そのまま横に置いて、床や卓の室礼にもなりましょう。松飾りはおひとつ、¥880。今月13日から店で販売致します。
さて、おかげさまでミニ大通りに根を付けて4年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。
まあ、確かに花の種類が少なく「ちょっと入りにくい」といわれることもありますが、時おり、「他とは違って入ってみたかったの」といってくださるお客様に救われる今日この頃。来年もどうぞ宜しくお願い致します。
えっ、ここで2012年3月で花屋になって20周年です、なんていおうとしたら、勘違いをしていて、それは今年の話だったなんて、そんなことはいいっこなしよ。(2011.12)
ミニ大通の並木から 2010
【マグノリアのボール】
フランスのインテリア雑誌や家具屋の目録をパラパラめくっていると、苔や月桂樹の葉、レンズ豆などで出来たボール型のオブジェがしばしば登場することがあります。その中で私が膝を打ってすぐに作りたい、と思ったのがこのマグノリアのボールです。
ポリスチレンの土台に葉を枝で刺して大胆に作られた姿を初めて見た時、まるで森の中から枝葉を拾ってきて、さっと仕上げたような印象を受けました。すなわち、良いブーケや花飾りがそうであるように、見た目がさりげなく自然であることは、オブジェにおいても人を魅了するというわけです。
マグノリアのボールはおひとつ、直径20センチ(写真)が¥3,675、直径15センチが¥2,100。そういえば、ユネスコ本部やプラネタリウムなど、パリの街では大きな球体が目に付きます。フランス人は球体が好きなのかなあ。(2010.1)
【スノードロップの鉢植え】
自宅用として、あるいはちょっとした贈り物として、店に並ぶ季節の小さな鉢植え。今月はスノードロップの登場です。透明なガラス器に3球のグループで植えて土の表面を苔で覆い、まだ雪が残る早春の庭といった雰囲気で仕上げています。
もっとも、神話の世界でスノードロップは冬から春への転換の象徴として、天使が雪のひとひらを掴んで息を吹き掛け誕生した花でありましたから、この鉢植えは窓辺に飾って、雪景色とともに眺めるのが一番でありましょう。おひとつ、¥1,050。
さて、2月2日はキャンドルマス。冬の終わりを告げるクリスマス最後のカトリックのお祭りですが、私が以前から特別な関心をいだいているのは、たくさんのろうそくの灯だけではありません。教会の祭壇にスノードロップを撒き散らす伝統的な花飾りの習慣です。やってみたい!(2010.2)
【花のポストカード】
ミニ大通りの並木と対話しながら、店に置く花や枝葉の種類を変えているように、壁際に並ぶ花のポストカードも、撮りためているフィルム写真の中から、ブーケや鉢植え、花飾りなどを季節に合わせて選んでおります。
これらの写真は、後で参考にするために10年ほど前から撮っている、いわば私の日記みたいなもの。花は料理でいうルセットのような記録を残しても、再び同じものができるとは限りませんから、常に写真で過去の良い感覚を確認しているというわけです。
もっとも、花のポストカードは「ああ、この人が作る春のブーケはチューリップやラナンキュラスをスノーボールと組み合わせる、17世紀のフランドルの画家たちが好みそうな雰囲気だわ」といった花選びの見本にもなりましょう。1枚150円。ちなみにこの写真は2001年の春のブーケから。(2010.3)
【ブーケの宅配】
「30cm四方のダンボール箱に、ゼリーで保水した花束を器に飾り、丸めた新聞紙を薄葉紙でくるんだボール状のクッションを箱の中に敷き詰めて固定。天地無用と冷蔵のシールを貼って準備完了!」とまあこんな具合に、札幌市外に花をお届けする場合は器付ブーケを宅配便で発送しております。
考えてみれば、スパイラルブーケはもとより花を持ち運びやすくするために生まれた花束ですから、移動で花が崩れるという心配はありません。また、器に入れることで花束を安定した状態で運べますから、器付ブーケが宅配にはぴったりだというわけです。
もっとも、気に入ったブーケだからこそ、たとえ遠くであっても届けてほしいということでありますから、いつも通りのものを発送するということが大切でありましょう。なお、花の鮮度を考えて、宅配は翌日到着地域に限ります。予めご了承ください。(2010.4)
【シャクヤクのブーケ】
シャクヤクはフランスで「聖母のバラ」、イタリアやスペインで「山のバラ」と呼ばれるように、バラのように美しい花として5月の私たちを幸せにしてくれますが、この花をブーケにするとなれば、フランスの花屋がしあわせの印と呼ぶ、少し開きかけの状態で束ねたいところ。
そして、伝統的にシレーヌやアルケミラ・モリスと合わせたり、現代的にラズベリーの枝葉を添えてみたり、写真のようにキソケイで庭から摘んだように仕上げれば、その豪華な花姿が良くひき立つというもの。
もっとも、最近は切り花の季節感が失われてきていて輸入のシャクヤクが冬に出回ることもありますが、たとえば、毎年5月に開催される自転車ロードレース「ジロ・ディ・イタリア」でのシモーニやクネゴのように、この花もやはり5月の光が良く似合います。(2010.5)
【夏のミニ大通り】
ミニ大通りは、植物園から道路を挟んで西におよそ900mほどの並木道です。中央分離帯が幅のある遊歩道になっていて、春は桜が楽しめたりしますが、店のある西17丁目には桜がありません。しかし、クルミやドングリ、姫リンゴ、サクランボといった果樹があって、夏から秋は賑やかな並木となります。
一般に札幌の街路樹は、その気候風土から強選定をするため、高さが抑えられ枝振りも暴れ、夏でも緑が少ないといわれますが、ミニ大通りの樹木は大きく育っているため、店の前の建物が隠れるほど緑の密度が高く、夏は森の中といったところ。
6月ともなれば、店のドアを開け放し、京都は東山のとある宿のごとく、木々の葉音や鳥の鳴き声を店のBGMにするのが私の夏の楽しみです。ちょっと自慢をすれば、風が抜ける店内でブーケが作られる花屋はそんなにないと思うんだなあ。(2010.6)
【アジサイを夏のリビングに】
以前はオランダから手に入れるしかなかった特別に栽培されているアジサイも、最近は北海道でも作られるようになり、この季節に欠かせない存在になりました。考えてみれば、白やライム色のアジサイは隣家の庭でもそう見掛けませんから、これは夏の贅沢品というわけです。
ただ私は、最近流行の、アジサイをバラなんかと丸くまとめるロマンチックなブーケには何だか興味がありません。やはり写真のように、ミントやフランボワーズ、スモークグラスといった夏のアクセントに、その質感が調和するモルセラを加えたバロック風な仕上げが好ましいところ。
もっとも、アジサイを夏のリビングに飾れば、それだけで、ロワ-ル地方の宿にいるようなバカンス気分に浸れます。後はロゼワインを片手に、テレビのチャンネルをツール・ド・フランスに合わせたりしてね。(2010.7)
【薔薇の香りを楽しんで】
花屋の薔薇といえば、香りが弱いという印象がありますが、夏の間はイングリッシュローズのように、香り豊かな品種の薔薇を楽しむことができます。
たとえば、象牙色のフェアー・ビアンカは、オールドローズやミルラの香りです。房咲きですから、ブーケはもちろんのこと、1枝を部屋に飾るだけでもロマンチックな気分に浸れます。
それから、シャクヤク咲きで牡丹色のイブピアッチェ。まるでローズガーデンに迷いこんだような強い香りがあります。写真のように、山ゴボウや、八重咲きのコスモス、フランボワーズなんかと田舎風に束ねれば、もし夏のピクニックにブーケを持って行くことになった時にも、ぴったりでありましょう。
もとより、薔薇は西アジアの暑い地域が原産の花ですから、夏こそ薔薇の香りを楽しんで。(2010.8)
【シンフォリカルポス】
舌を噛みそうな名前のシンフォリカルポスは秋のブーケや花飾りに、ちょっとした田舎の趣を与えてくれます。考えてみれば、花屋に出回るこういった愛らしい小さな白い実を持つものは他にハゼやペルネチアの鉢植えぐらいかもしれません。
もっとも、この白い実はバラやリシアンサスと喜んで混ざり合ってくれますが、とりわけ、くすんだ緑色のアジサイと束ねますと秋の田舎が感じられます。ちょっとだけ束ねて、自宅用、あるいは秋の手土産としても素敵ですから、きっといつの日かこの組み合わせが流行すると信じて、毎年9月には写真のように店内に並んでいるというわけです。
シンフォリカルポスといえば、岩見沢市の宝水ワイナリーからローズガーデンに抜ける道路沿いの田舎で、秋の白い光を浴びている姿を目にすることができます。そう、この道は私の秋のサイクリングコース!(2010.9)
【秋に作る蘭の鉢植え】
たとえば、ファレノプシスにせよ、パフィオ・ペディルムにせよ、バンダにせよ、蘭と聞くと、皆さんの中には、季節を問わずホテルやちょっと洒落た感じの現代風の花屋に並んだ、コスモポリタンな花と思われる方も多いかも知れません。
あるいは、19世紀フランスの作家ユイスマンスが小説に書いているように、暖房のガラスの宮殿に住む高貴な花、造花を真似た自然な花という印象もありましょう。
私もそんなイメージがありましたから、写真のような蘭の鉢植えをパリの花屋で知った時、ずいぶん感心しました。ネコヤナギの枝、マグノリアの葉を加えるだけで、こんな素敵なものができるなんてね!
秋に作る蘭の鉢植えはおひとつ¥4,200。ネコヤナギとマグノリアが出回る10月の終わりに今年も登場します。(2010.10)
【モミのガーランド】
申すまでもなく、クリスマスは12月25日だけを突然お祝いするわけではありません。シュトレンなんぞを少しずつ食べながら、気分を盛り上げていくものです。然れば、花屋も11月はリースやクランツを作るなど、クリスマスの準備が始まります。
私の準備はといいますと、良いヤドリギを探して、マグノリアのボールを用意して、ヒヤシンスの球根を集めて、そしてこのモミのガーランドを作るというわけです。モミの枝を手のひらほどに切り分けて、リトアニア産の細く目立たない麻紐で長さ70センチほどに束ねて仕上げます。
もっとも、これはアドヴェントを知らせる印でもありますから、1ヶ月ほど楽しめることも大切です。おひとつ、¥2,100。木蔦やイレックスが溢れ、ジュニパーの香りが漂い、店内が冬の森となる今月中旬に登場いたします。(2010.11)
【クリスマスのリース】
静かなミニ大通りで店を構えて良かったことは、鳥の鳴き声を聞きながら花を束ねられるだけではありません。訪れた人とのゆったりとした会話の中から生まれる新しいアイデアがあります。
モミ、ネズ、ヒムロスギ、そして雪を冠ったような蕾のユーカリ・グロボラスをラフィアで束ねただけのクリスマス・リースもそんな時間に思い付きました。森の良い香りが楽しめて、いつものブーケと同様に凝った印象がないように仕上げます。直径20センチ。おひとつ、¥2,100。
さて、早いものでミニ大通りでブーケを作り始めて3年が経ちます。有り難うございました。来年も宜しくお願い致します。
えっ、このリースといい最近やっと世の中の人の嗜好や希望がわかってきたようですね!なんて、そんなこといいっこなしよ。(2010.12)
ミニ大通の並木から 2009
【小さなブーケ】
小さなブーケにはいろいろな考え方や作り方がありまして、最近もっぱら見掛けるのがブーケをそのまま小さくしたようなミニサイズの花束。でも私の好みにぴたりと一致するのは小さな花や果実だけを束ねたものです。
スミレ、デージー、スズラン、忘れな草、野いちご、ナスタチウム、シクラメン.....
大きく束ねられないからこそ小さな束にして色や香りを楽しむ考え方、そして花の周りに葉を王冠のようにぐるりと添えた作り方。もうずいぶん昔に訪れたフランスの花屋にはこんな心を贅沢にさせる愛らしいブーケが60フランほどで並んでいたというわけです。
そんなことを思い出して作る小さなブーケはおひとつ¥1,260。写真の小さな赤いバラなんぞは相手に負担のかからない還暦祝いのちょっとした贈り物にも最適です。(2009.1)
【雪どけの花器】
トリュフチョコレートを作る時のトランペの要領で、円筒形の透明なガラス器にパラフィンろうを薄くコーティングすれば新作『雪どけの花器』の完成です。白い不透明な外観と液状のような質感から「雪どけ」と名付けましたが、理由はそればかりではありません。
たとえば、ヒヤシンス、チューリップ、ラナンキュラス、スイセンといった春の花をこの花器に飾れば、まるで雪どけの中から咲いているような雰囲気にもなるからです。それは、フクジュソウやフキノトウが雪どけの中から姿を現すような、雪国の早春の情景でもありましょう。
大きさは高さ11センチ、直径6センチほど。ベッドサイドに飾るような小さなブーケならちょうど良く飾れます。おひとつ¥630。
この写真を見る限り、ヒヤシンスとチューリップは何だか嬉しそう。ブロカントに収まったスノードロップはちょっと悔しそう。(2009.2)
【花の定期契約】
あらかじめ飾る場所や花器を相談して花を飾る花の定期契約。現在は週に1度、店から徒歩圏内にある鍼灸院と手作り石鹸の工房にお届けしています。いずれもミニ大通の近くなので、何かあった時にも馳せ参じられるというわけです。
もっとも、それぞれの店主に代わって季節を運ぶわけですから、こういう時の花飾りは、誤解を恐れずに申せば、花屋が技術を見せてしっかり飾りました、ではいけません。あたかも店主が飾ったように、何気なくそこに季節が感じられる雰囲気になることが大切です。でもそれがなかなむずかしいのではありますが・・・。
ちなみに、花の定期契約のことをアボンヌモンともいったはずで、ちょっと調べようと思ったら、今年復活した自転車選手、ランス・アームストロングが今テレビで見事な走りをしている真っ最中。フランス語の勉強はまたこの次にしてと。(2009.3)
【花のレッスン】
2000年4月のこと。私が花のレッスンを始めることを知った周囲は不安がりました。そこで、「スパイラルブーケの難しい花材の組み合わせと分量は予め用意するのだから大丈夫」と説明したところ、いやはや、この私が人に教えることが心配なんだといいます。とまあそんな与太話はこれぐらいにして。
この花のレッスンは、資格を取るとか、人前で発表するとか、明日の花屋を育てるとか、ではありません。森の中で、田園で、自分の庭で、プリニウスの博物誌やユイスマンスの植物話を思い出すなんぞしながら、花や枝葉を摘み、鼻歌混じりにブーケが作れるようになることが目的です。本当かなあ。
スパイラルブーケには〈ブケ・ア・ラ・マン〉という呼び方があります。フランス語で「手の中で出来上がるフラワーアレンジ」というほどの意味で、すなわち、これは手が学ぶレッスンでもあるわけです。(2009.4)
【私の庭づくり】
庭づくりは、いわば永遠のデコレーション。依頼をうければまずはその場所を訪れます。そして第一印象を元に、hibariというピアノ曲なんかを聴きながら、古代バビロニア人の空中庭園のごとく想像を膨らませて、まだ見ぬ庭の完成図を描きます。
たとえば、フィンランドの地名が店名のカフェの庭には亜麻やクランベリーで北欧の森の雰囲気に。軟石が鎮座するフランス料理店の中庭にはハーブを添えてオーブラックの大地のように。カフェが併設するお宅の庭には店名にちなみ徒然草に登場する禾本科植物を中心とした素朴な野原を、という具合。
そして、今度は現実的に、北海道の気候風土や日照条件に合う植物を選び、5月下旬から植栽してひとまずできあがり。あとは自然におまかせです。お気付きのように、店、ブーケ、花飾りと同様に、私は庭においても、花や色がいっぱいにはならないんだなあ。(2009.5)
【高さのある器付きブーケ】
葉を巻いた器にブーケをセットした器付きブーケも、夏から秋の間に限っては旬のデルフィニウムの花で、高さのあるものが登場です。たとえば、写真のように、トクサを巻いた器に、デルフィニウムを田園調に束ねたブーケを飾るといった具合。すなわち、丸い花なら丸いブーケにするように、高さのある花なら高さのあるブーケにするわけです。
デルフィニウムといえば、皆さんの中には、今から20年ほど前、高橋永順さんによってその美しさを知った方もいるのではないでしょうか。実のところ、私もそんな一人で、野草風のアレンジに憧れましたっけ。
ちなみに、フランス語で田園風というほどの意味のブーケ・シャンペトルを作る上でも、デルフィニウムは欠かせない存在ですが、詩人の春山行夫さんによれば、フランスでこの花の花言葉は「野原の喜び」です。
永順さんも知っていたのかなあ。(2009.6)
【夏の自然】
夏の自然といえば、数年前に訪れた札幌の白旗山を思い出します。そこは、あらゆる緑が溢れる中、ひっそり群生する野苺、風に揺れるヤナギラン、草むらで踊るイケマ、光輝く水たまり、とまるでタルコフスキーの映画『ストーカー』の一場面のような、田舎とも違う非日常を感じる場所でありました。
それからというもの、私は夏のブーケや花飾りを作る時はさまざまな緑の交錯を心掛け、花や果実はそのアクセントと考えています。面白いことに、夏の緑はごちゃごちゃに混ぜ合わせても大丈夫。ご覧のとおり、時には野菜だってブーケになるわけです。
もう一つ、夏の自然といえば、ツール・ド・フランスがあります。自転車ロードレースのテレビ中継ではその土地の自然を満喫できますから、私は毎年フランスの夏の自然も味わっているようなもの。もっとも、今年は新城選手がアタックなんぞした日には、もう景色どころではありませんね、皆さん!(2009.7)
【シリンダー型のガラス器】
たとえば、シンプルな形の白い食器は、季節や料理を選ばない何にでも合う一枚として、皆さんのご家庭にもあるかと思います。そんな白い食器のように、使い勝手の良いフラワーベースといえば、このシリンダー型のガラス器です。
今の季節なら、アジサイやモルセラが良く似合うでしょうし、季節の果実を飾っても素敵かなあ。もっとも、ツェツェの名高い「四月の花器」や、ジェフ・リーサムの花飾りのごとく、いくつか並べれば、現代風の洒落たデコレーションも簡単に出来上がります。恐るべき、シリンダー型のガラス器たち。
写真の高さ25cmはおひとつ、¥1,470。ちょっとしたブーケも飾れる大きさです。また、私の花飾りで最近よく登場する高さ80cmはおひとつ、¥10,815。こちらは床に置いて、ドウダンツツジなんぞを飾れば、ご自宅にも夏の森が訪れます。(2009.8)
【私の花飾り】
花飾りの依頼を受けた時、まず確認することが二つあります。一つはその目的です。たとえば、結婚式やパーティー、発表会なら華やかな雰囲気に。教会なら厳粛に。作品展や店飾りなら周りを引き立たせる控え目な印象に。といった花飾りが求められます。
もう一つは、花飾りの分量です。事前に飾る場所を訪れたら、人の導線にそって花が必要なところを探し出します。そして、飾る期間や環境、準備できる花材や花器を考えた上で、スケッチを描くというわけです。もっとも、どんな条件であっても、私の花飾りになっていることが大切でもあります。
写真は今月始めに行った結婚披露宴の花飾り。長さ113mの客席を白い花とキャンドルで包みました。もとより、私はホテル内の花飾りから今の仕事を始めたので、これは私の原点のようなもの。ところが今回は筋肉痛に。花飾りは経験とともに、体力も必要です。(2009.9)
【2つのガラス器】
細長いグラスの上下2箇所をラフィアで結べば、新作の花器『2つのガラス器』の完成です。繋げたことで、ただのグラスが飾りやすいフラワーベースに変化しました。まあ、ガラス器に葉を巻くのと同様に、身近にあるものを花器に仕上げるのは私の好むところ。
たとえば、2つ繋げれば安定感が生まれますから、グラス1つでは倒れる豆柿の枝葉なんぞも、しっかり飾ることができます。また、グラスの内径は5.5センチあって、小さなブーケも収まります。そして高さが使いやすい15センチで、名高い「四月の花器」と同じというわけです。
写真は結婚式の花飾りで、この花器にアイビーを絡めたところ。結婚を象徴するアイビーで2つのグラスを結ぶなんて洒落てるでしょ。おひとつ¥420。アイビー付きは¥840。今月のレッスンでは、これを使ったデコレーションもご紹介致します。(2009.10)
【クリスマスローズの鉢植え】
セドリック・クラピッシュの映画「パリ!」の中で、冬のバルコニーいっぱいに咲いていた白い花こそ、クリスマスローズの鉢植えです。申すまでもなく、この花は寒空とクリスマスの季節を好み、私たちの心を豊かにしてくれますから、アドヴェントには欠かせない存在でありましょう。
しかしながら、私の住む札幌では近づくクリスマスの時期は朝晩の冷え込みが厳しくなる為、あの映画のようにバルコニーで、あるいはフランスの作家コレットのように雪の積もる庭でこの花と対面する、というのはちょっと難しい。無暖房の室内に飾って楽しむのが一番良いみたい。
写真のように、鉢は藁で巻いてあたかも中世の絵画のような印象で仕上げたクリスマスローズの鉢植えはおひとつ¥3,990。モミやネズの枝葉で店内が針葉樹の森となる11月中旬から今年も並びます。(2009.11)
【球根型のろうそく】
太陽の化身としてクリスマスの時期にかかせないろうそく選びも、ブーケの傍らで灯すとなれば案外難しいものです。たとえば、香りがあっては花の邪魔になりますし、ファンシーな色や形も避けたいところ。しかし、ありきたりのものでは面白くありません。
そこで、北海道美幌町でコーヒーとろうそくを提供する「喫茶室豆灯」に特注して作っていただいたのがこの球根型のろうそくです。ゆかしい色合いに、自然の生命力を感じるフォルムに、思わず手に取りたくなるのは私だけではないでしょう。おひとつ(大)¥650、(中)¥480、(小)¥320。
さて、おかげさまでミニ大通りでブーケを作り始めてもうすぐ2年目を迎えます。有り難うございました。来年も宜しくお願い致します。
えっ、今年はこっそり休んでサイクリングをしていたなんて、そんなこといいっこなしよ。(2009.12)
ミニ大通の並木から 2007、2008
【ヒヤシンスの鉢植え】
ヨーロッパの夏の窓辺を飾るのがゼラニウムの鉢植えならば、冬の部屋を彩るのがヒヤシンスの鉢植えです。その強い香りは好き嫌いもありますが、水耕栽培で育てた経験のある私たちにとっては、馴染み深い花でありましょう。
写真は私がこの時期に作るヒヤシンスの鉢植えです。大山木の葉で包んだ鉢に球根が少し見えるようにヒヤシンスを1本飾り、苔をあしらいます。こうすれば、花がしっかり支えられ、土も隠せるというわけです。
もっとも、このようなヒヤシンスの鉢植えはヨーロッパの花屋ではよく見掛けられます。フランスの花の本に「ヒヤシンスは鉢植えに1本が最も美しい」とあったのも納得です。
ちなみに、このヒヤシンスの鉢はクリスマスの頃に蕾であれば、新年にちょうど咲いてきます。年末年始のちょっとした贈り物にも最適です。(2007.12)
【ろうそくの花器】
2001年の春、「花器の提案」というギャラリーの企画展に参加することになって制作したのがろうそくの花器です。パラフィンろうを型に流し固めて作りました。
花器の形は大きさの異なる4種の四角柱。花や枝葉を飾る実用性と、積み木のように積み重ねて使うことを考えました。また、規則的な形だと手作りならではの歪みがより明確となります。プラリネのチョコレート、とまではいかなくても、ひとつひとつ微妙に違うのがこの花器の愛らしいところ。
もっとも、湯煎に掛けたり、時間と温度によって仕上がりが変わるなど、その作業はチョコレート作りと似てなくもありません。
先日、あの時の展示で買ったというお客様から、また作ってほしいと依頼を受けて、再び作り始めたろうそくの花器。注文をいただいたことはもちろんのこと、ずっと使ってもらえていたことが嬉しくて嬉しくて。おひとつ¥1,785(小)からの受注製作ですが、店頭にも今は少しだけ並んでいます。(2008.1)
【「四月の花器」を使ったレッスン】
写真は先日のレッスン、「四月の花器」を使ったデコレーションで見本に作ったものです。チューリップとヒヤシンスの花に、ネコヤナギ、ロウバイ、ユーカリの枝葉を飾り、アクセントにレモンを添えています。
この「四月の花器」に花や枝葉を飾ることで、花と器のバランスや色合わせのコツが良くわかります。もちろん、花器はレッスン時にこちらでお貸ししていますので、「4月の花器」をお持ちでなくても、レッスンにご参加いただけますのでどうぞご安心を。
ちなみに、「四月の花器」にはパリの花屋クリスチャン・トルチュが一目見て50個注文したとか、ポンピドゥー・センターのコレクションになっているとか、私も12年間愛用しているといったエピソードがあるわけですが、一度この花器を使ってみれば、さもありなんと納得されることでしょう。(2008.2)
【クロッカスの鉢植え】
花はその種類によって、切り花やブーケとして楽しめるもの、庭で眺めたり鉢植えとして楽しむべきものがありますが、切り花にはあまり向かないクロッカスの花はまさに後者でありましょう。春が近づくと私は写真のように白いクロッカスを少し小振りのテラコッタの鉢に飾ります。
テラコッタとはイタリア語で焼いた土というほどの意味ですから、クロッカスのように背丈のない大地との距離が近い植物には良く似合います。たしかイギリスの花屋ジェーン・パッカーの言葉だったと記憶しますが「テラコッタは土を連想させる」というわけです。
クロッカスの花は、ヨーロッパではかつて結婚式に飾る習慣があったように、始まりの象徴でもあります。庭で群生する美しい姿も素敵なものですが、この小さな一鉢が部屋の中に春を運んでくれることでしょう。おひとつ¥660、3月が旬です。(2008.3)
【スズランのブーケ】
ご存じの方も多いと思いますが、5月1日はスズランの日といって、この日にスズランを手にした人にはその1年、幸せが訪れるといいます。フランスではスズラン売りが街に現れるようで、街で売るスズランを早朝の森で摘む場面がある映画は「クリクリのいた夏」だったでしょうか。
写真は今から10年ほど前に作ったスズランのブーケです。ちょうどアジアンタムの葉を添え始めた頃で、現在よりも少し控えめではありますが、スズランのブーケは昔からこんな雰囲気で作っています。もっとも、当時はスズランの日を知る人も少なく、毎年買いに来てくれたのは忍路のパン屋さんぐらいだったでしょうか。
さて、今年のスズランのブーケはレッスンに併せて4月29日(火)から店頭に並びます。写真より小さい束なら、おひとつ¥1,890。今年も幸せが届きますように。(2008.4)
【ブーケ・マリアローザ】
母の日は日本では5月の第2日曜日ですから、私が毎年、母の日に作るブーケはもっぱら薔薇が主役です。北海道で栽培された薔薇がちょうど出回り始める時期でもありますし、申すまでもなく、薔薇はスパイラルブーケに適した花でもあります。
また、シャクヤクが「山の薔薇」と呼ばれることや、スノーボールのように学名に薔薇の意味であるロゼウムと付いた花が多くあることからも、薔薇がしばしば美しさの比喩となっていることが判ります。ヨーロッパで母の日に薔薇を贈るのも、そのためかもしれません。
表題にあるマリアローザとは、5月にイタリアで3週間開催される自転車ロードレースの勝者が着用するローズ色のジャージ名で、5月の薔薇のブーケを私は勝手にこう呼びます。200人の集団が自然の中を走る自転車ロードレースもまた薔薇のように美しいもの。とまあ今年も私の5月は薔薇でいっぱい!(2008.5)
【ブーケ・シャンペトル】
オート麦などの禾本科植物が出回り始めると、ブーケ・シャンペトルの登場です。シャンペトルとはフランス語で「田園の」というほどの意味で、パリの花屋で見かけるブーケの一つで、シャスタ・デージーやスカビオサ、リシアンサスといった田園に咲く背丈のある花がよく似合います。
また、ブーケは小さくまとめず、抱えるほどの大きさで仕上げた方がより田園の雰囲気になりましょう。もっとも、このブーケには田舎で摘んだ雑草を組み合わせるやり方がありますが、私は様々な経験から、近年は花市場で手に入る栽培されたもので作ることにしております。
写真は2年前の夏に作った花嫁のブーケ・シャンペトルです。花の茎もオート麦で包みましたから、麦を100本は使ったでしょうか。きっと花嫁が歩くたびに、カサカサと麦の祝福の声が聞こえたにちがいありません。(2008.6)
【ラベンダーのブーケ】
夏のテーブル飾りに重宝するこのラベンダーのブーケ。白と緑のブーケしか作っていなかった以前の花屋「レ・フルール」でも作っていましたから、見覚えのある方もいらっしゃるでしょう。誰でも簡単に作れるブーケですから、ここでその作り方をご紹介いたします。
材料は、乾燥したラベンダーが400本と、直径5cm、高さ12cm程の円筒型グラスです。作り方は、両面テープを使ってグラスのまわりをラベンダーで覆います。この時、花の高さを揃えることが大切で、しっかりと覆ったら後はラフィアで縛って完成です。
もうずいぶん昔、パリの花屋が作っていたのを、見よう見まねで作り始めたこのブーケ。ラフィアを2箇所縛るのが私のゆずれないところ。今年も7月下旬から私が作ったものが店内に並びます。おひとつ,¥4,200。予約も承ります。(2008.7)
【日々、ブーケを作り置くこと】
ヨーロッパの小さな花屋を見習って、開店以来、日々、ブーケを作り置いています。いわば、見本ともなる本日のブーケといったところですが、小さな花屋にとっては、品揃えや店飾り以上に、出来上がったブーケがその店を知る指標となるからです。
たとえば、こういう色合わせをするのかとか、季節の花で勝負しているのかとか、流行にとらわれず田舎風の仕上げなのかとか、夏は殺菌作用があるミントを加えているのか、といったその店ならではの考えも、ひとつのブーケから読みとれます。
ちなみに、私が作り置くのは白い花のものと、写真のように季節がもたらす色のもので、この日はモーブ色のリシアンサス(トルコギキョウ)のシャンペトル風ミント添え。イギリスの庭師の服を連想させる上品な夏の色合いは、グラインドボーン音楽祭にも持って行けそうでしょ、皆さん!(2008.8)
【果実が入ったブーケ】
ハプスブルク家の宮廷画家、アルチンボンドの『四季』は人間の横顔を植物で組み合わせた肖像画です。春は花、夏は禾本科植物や野菜、秋は果実、冬は枯れ枝や常緑樹で描いています。マニエリスム時代の嗜好として、私たちの四季のイメージを追い求めた結果というわけです。
9月に入れば、色付き始めた姫リンゴ、木イチゴ、山ブドウ、千成ホオズキ、ククミスの果実が夏の間はちょっと退屈だった店内に、自然の楽しさを思い出させてくれます。そのまま器に飾ってもガラス皿に並べるだけでも絵になる果実は、自然から私たちへの秋の贈り物というわけです。
誕生日、発表会、敬老のお祝い、結婚記念日、送別会、招かれた時の手土産、ツール・ド・北海道の表彰式。この時期のブーケに果実が入っていれば、贈られた人はきっと喜ぶに違いありません。(2008.9)
【マグノリアのリース】
マグノリアの葉を土台に巻き付けて、花や針葉樹を飾ったりするのが、私が唯一作っているリースです。ご覧のように、マグノリアの葉は枝で固定して、試験管は枝に引っ掛け、針葉樹は巻き付けた葉の隙間に差し込みます。つまり、接着剤やワイヤーなど不要で出来上がります。
もっとも、リースはプリニウスの時代では贈り花であって、今日でいうブーケのようなものでした。いわばマラソン選手に贈られる月桂樹や夏至祭のツェッペルのように、素材を束ねたり重ねたりして、自然な雰囲気で作る事が大切というわけです。
写真は、実際にバレエの発表会に届けたもので、ユーチャリスの花を飾って仕上げました。壁掛けにもテーブル飾りにもなるこのリース。今年は10月下旬より店頭に並びます。ちなみにここでいうマグノリアは大山木。東京の原美術館そばに大きいのがあったなあ。(2008.9)
【ネズの入荷】
店の近くにある近代美術館のヤドリギが現れるようになれば冬の始まりです。季節の花が少なくなるこれからの季節、ブーケの主役はむしろ常緑樹なのかもしれません。
実の成る木蔦やミルト、個性的な蕾を付けるユーカリやスキミア、暖かみを感じるモミやヒバなど、その多くは野山からの収穫で野趣に溢れ、初冬のブーケには欠かせない存在です。花材のジビエとでもいいましょうか。
中でも楽しみなのは、イタリアの魔女除けのお守りとして、グリム童話として、ビョークの映画として、あるいは、蒸留酒ジンの香り付けとして私たちに馴染み深い西洋ネズの枝葉が、この時期に少しだけ入荷することです。
写真は、房咲き水仙と常緑樹を束ね、フェネスサカモトの音楽を聴きながら、ネズの入荷を待ち望む11月、冬の朝。(2008.11)
【ミニ大通りの花屋】
静寂な冬の並木。小鳥のさえずりがBGMとなる春の並木。木漏れ日が気持ち良い夏の並木。ヒメリンゴやクルミが賑わう秋の並木。ミニ大通りを眺めながら、ブーケを作り始めて一年が経ちました。
はたしてこの一年、「森の中でこっそり咲く花を見つけたような気分」の花屋になっていたのかどうか心配ですが、おかげさまで二度目のクリスマスを迎えることができます。有り難うございました。
写真は、エゾ松やネズが店内を包み、キャンドルの灯とクリスマスローズの鉢植えが暗闇に浮かぶ、12月のミニ大通りの花屋です。
えっ、ヤドリ木が飾られてないって?そんなこと言いっこなしよ。
来年も宜しくお願いいたします。(2008.12)