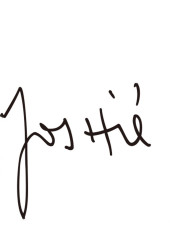ミニ大通の並木から 2022
【スペシャルレッスンについて】
「時にはたくさん束ねてみよう」という事で昨年から定期的に始まったのが、スペシャルレッスンです。たとえば、春なら色とりどりのチューリップや何種類かのクリスマスローズを。初夏ならシャクヤクが外せません。
また、夏になればバラをカラフルに仕上げたり、秋にはダリアやアジサイ、冬ならアネモネといった具合です。場合によっては、器とセットで仕上げるのも、このレッスンの醍醐味でありましょう。
もっとも、スペシャルと聞けば何だか難しいと思われがちですが、スパイラルブーケは、ある程度の花の数があった方が作りやすいので、慣れてしまえばこちらの方が簡単です。そして、出来上がった時の気分もスペシャルになるのはいうまでもありません。(2022.2)
【近ごろのラナンキュラス】
近ごろのラナンキュラスは花姿や色も豊富で、数年前とは比べ物にならないくらい、日本で多くの品種が作出されています。とりわけ、私が好んでいる新しい種類ほど、その名前がフランスの自治体や景勝地にちなんでいることが多く、何だか興味深い。
ロシェル、セルベール、モルヴァン、マイエンヌ、ロンシャン、オルレアン、グルノーブル、アンディーブ、ルルド、ラマノン、ボーヌ、モンタンヴェールなどがあり、エシレにいたっては覚えやすいバター色の品種だったりします。
ちなみに、写真のものはアルプスの麓にある名高いスキーリゾート地の名前、クールシュヴェルという品種で、小ぶりな蕾とスノーボールとの相性の良さは「ジス・イズ・ラナンキュラス!」と叫びたくなる逸品です。(2022.3)
【花の咲くところ】
シリアの首都ダマスカスで自生していた香り良いバラをダマスクローズと呼ぶように、私たちに馴染み深い花は世界の思わぬところで咲いています。
たとえば、シクラメンが国花であるパレスチナ。アネモネなど聖書やギリシア神話に登場する植物は乾いたこの土地が原産です。よく聞くガザ地区にはヒナゲシが群生しています。
それから、赤いチューリップが国花であるアフガニスタン。野生のライラックやジャスミンがあることはあまり知られていないでしょうか。
そして、この写真のブーケで束ねているヒマワリとビバーナムが国花のウクライナ。国旗の黄色は小麦を表し、映画「ひまわり」の舞台となったことはいうまでもありません。(2022.4)
【ブーケ・ロンについて】
ブーケ・ロンとはフランス語で「丸い花束」というほどの意味です。今から50年ほど前、パリの花屋のジョルジュ・フランソワやアラン・シャンフェランニが始めた茎をスパイラル状に束ねて作るブーケは、今日、私たちにも身近な存在です。
「それまでのものは綺麗ではなかったから」と考案者がいうように、この丸い形は、どんな花瓶にも飾りやすく、どこから見ても美しく、どこにでも運びやすいのはいうまでもありません。
ちなみに、ブーケ・ロンの派生として、野菜を用いるものや、花を種類ごとにまとめるグルーピング、クリスチャン・トルチュが禾本科植物なんかを加えて田舎風に発展させたブーケ・シャンペトルなどがあります。(2022.5)
【父の日のブーケ】
黄色いバラを父の日に贈る慣習は日本特有ですが、これには理由があります。今から40年ほど前、日本の経済団体が父の日の販促として、黄色をテーマカラーに制定しました。
そこで、当時の花屋はそのキャンペーンに乗じて、黄色いバラをこの機会に売り出しては、と画策します。なぜなら、黄色いバラの花言葉は「嫉妬」で、贈り物としてはとかく敬遠されていたからです。ただ残念なことに、現状では母の日のカーネーションほど定着はしていないかもしれません。
とはいえ、6月の第3日曜日はバラが旬を迎える頃で、相性の良いビバーナムも出回る季節です。ご覧のように、他の色のバラが妬むほど、黄色いバラのブーケが美しく仕上がるのはいうまでもありません。(2022.6)
【エピ・ド・ブレ】
エピ・ド・ブレとは、フランス語で麦の花穂というほどの意味で、一年中お金と幸運に恵まれるようにと、麦を7月7日7時に7本刈り取って家の中に飾る習慣です。聖ヨハネの麦とも呼ばれるのは、この行事も夏至に関係しているからでありましょう。
そこで、このエピソードに由来して、7月は麦をご用意しています。7本束、ブーケ、そしてリースと、どんな形であれ、その黄金色は部屋はもとより、私たちの心も明るく照らしてくれるのはいうまでもありません。
ちなみに、麦おばさん、コルンムーメが現れるのもちょうどこの時期です。畑を守るべく、波のようにうねりざわめきながら、夏の美しい麦畑を駆け抜けていきます。(2022.7)
【白磁の花器ふたたび】
一見すれば、アンティークとか、古物とか、アノニマスといった言葉を連想させる、内藤美弥子さんが作る白磁の花器には、どこか控えめで、誰かに見つけてもらうのを待っているような佇まいがあります。
それは作品でありながらも親しみやすく、かといって商品と呼ぶのも似つかわしくありません。なぜなら、以前この欄でご紹介したように、オリジナリティ溢れる製作技法が、この唯一無二の花器を生み出しているからでありましょう。
4年半振りとなるこの夏の展示では、24点の新作が並びます。特筆すべきは、全てオーバル型だということで、縦横でその表情が変わり、置き場所を選びません。これもまた、内藤さんの優れたデザインでもあります。(2022.8)
【リリオペについて】
ギリシア神話に登場する水の妖精の名前がついたリリオペは、草丈が膝下ほどの常緑多年草で、懸垂する剣状の細葉が特徴です。夏から秋には花も咲きますが、花屋に並ぶのはもっぱら葉のみで、色は写真の濃緑の他に斑入りもあります。
パリの花屋、カトリーヌ・ミュレーはこの葉を紐のように結んで使い、クリスチャン・トルチュはギリシア神話に倣って、リリオペの息子であるスイセンと束ねることで、愛情豊かな母子のブーケに仕上げました。
ちなみに、花市場でリリオペはミスカンサスというススキの学名で流通しています。輸入先のスリランカではそう呼んでいるみたいですが、どう考えても、ススキとは別の植物であることはいうまでもありません。(2022.9)
【秋色のアジサイ】
秋色のアジサイとは、夏に咲いたアジサイの色が変化して、少し落ち着いた色合いになった状態のことを指します。むろん、気象条件によってその変化は異なるわけですが、この秋色のために、オランダでは様々なアジサイの品種改良が行われてきました。
といいますのも、ヨーロッパでは、アジサイが夏よりも秋に楽しむ花として人気が高いからです。美しく変化した低い彩度は、色づいた秋の実や葉と喜んで混ざり合います。ドライフラワーとしてではなく、ブーケとしての楽しみ方です。
秋色のアジサイはまた、雪国に住む私たちにとっては、近づく冬のサインでもあります。この花のレッスンを終える頃には、コートが手放せなくなるのはいうまでもありません。(2022.10)
【冬はアネモネ】
風が良く吹く早春に咲くことから、ギリシア語で風を意味するアネモネですが、この花は春よりも冬が似合う気がしています。花首をまとうパセリ状の葉がまるで襟巻きをしているようで、何だか、冷たい北風をしのいでいるではありませんか。
そういえば、ルノワールは多くの花の絵を残していて、晩年までアネモネを描き続けていました。しかし、彼の描くアネモネからは、春の暖かな光というよりは、冬の静寂な空気みたいなものが常に感じられます。
また、ゴダールもこの花に冬の季節を見ていたに違いありません。映画「女は女である」では、11月10日の暦がクローズアップされる場面がありますが、その部屋にはアネモネが活けられていたのも偶然ではないでしょう。 (2022.11)
【マジックアマリリス】
その説明書によれば、水も土も要らず、35日ほどで咲くというのが、オランダから届いた新品種のアマリリスです。奇術師マギーが拵えたかのように、マジックアマリリスと呼ばれています。
もとより、お客様からその存在を教えていただき、初めて仕入れたこの球根。一体どう咲くのか興味津々、新年の贈り物としても喜ばれそうです。
さて、お陰様でミニ大通に根を付けて15年が経ちました。皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。来年もどうぞ宜しくお願いいたします。
えっ、COVIT-19の抗原検査でネガティブが出たことに、その意味を勘違いして、もう一度検査したでしょって?まあ、そんなことはいいこなしよ。(2022.12)